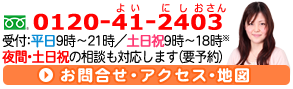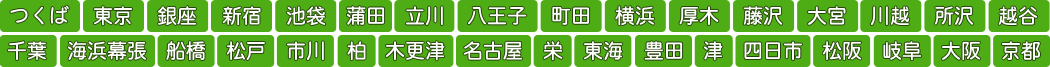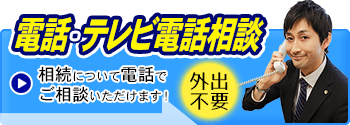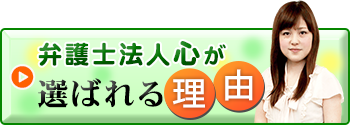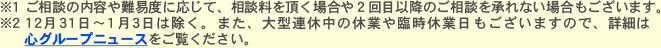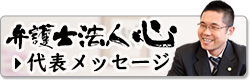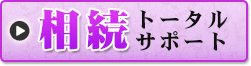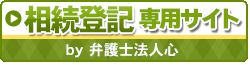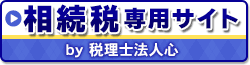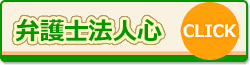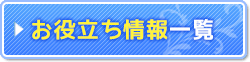遺産分割協議で相続人全員が揃わない場合の対処方法
1 不在者管理人の選任
遺産分割協議は相続人全員で合意をしなければなりません。
しかし、普段から連絡を取っていない場合など、元居た場所からいなくなってしまい、相続人の行方が分からなくなってしまうケースもあります。
そのような場合には、不在者財産管理人を家庭裁判所に対して申し立てることになります。
不在者財産管理人と遺産分割に関する内容は、こちらも参考にしてください。
もっとも、不在者財産管理人の本来の職務は、不在者の財産を管理することにありますから、遺産分割協議に参加するというのは、不在者財産管理人の本来の職務権限から外れることになります。
そのため、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには、別途家庭裁判所から許可を得ることが必要です。
次に不在者財産管理人が選任された後に、不在者財産管理人とその他の相続人とで遺産分割協議を行うことになりますが、当該協議では不在者の取り分が、法定相続分以上になるような遺産の分け方をしなくてはなりません。
不在者の取り分が法定相続分を下回るような内容の遺産分割協議をしたとしても、当該内容では家庭裁判所の許可が基本的には出ないことになりますので注意が必要です。
2 失踪宣告
失踪宣告とは、行方不明から7年間を経過した場合に(災害や遭難などの危機で生死不明の場合は危難が去ってから1年間)、家庭裁判所が、当該行方不明者を法律上「死亡したもの」とみなすという制度です。
参考リンク:裁判所・失踪宣告
失踪宣告の申し立ては、行方不明者の利害関係人のみが申立をすることができます。
例えば、相続人の一人に7年以上も行方不明の者がいて、相続手続を進めることができないという場合には、当該相続人は家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てを行い、家庭裁判所に認められれば当該行方不明者は「死亡したもの」とみなされることになります。
この場合、当該行方不明者は法的に死亡したものと扱われますので、遺産分割協議は当該行方不明者を除いた相続人同士で行うことができるようになります。
相続人が行方知れずになっている場合、遺産分割協議を進めることのハードルは高くなります。
相続人が行方知れずになっている場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。