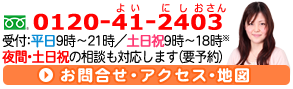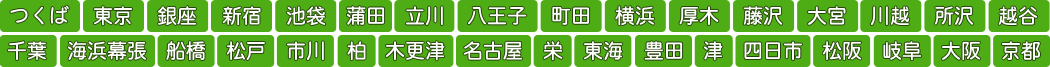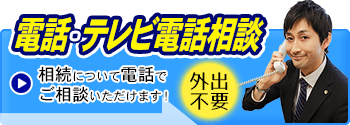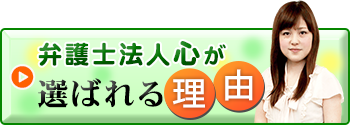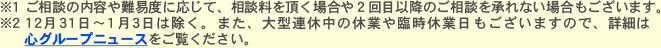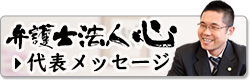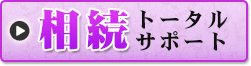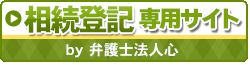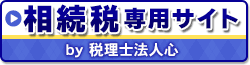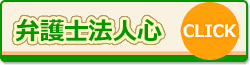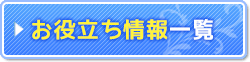遺産が不動産のみの場合の遺産分割の方法
1 不動産の遺産分割はたいへんなことが多い
不動産は金銭(現金や預貯金等)と比べると分割が難しい財産になります。
遺産分割を行うときは、相続人間で話し合いを行い、誰が何を取得するかを決める必要がありますが、逆にいえば、話し合いでまとまるのであれば、どのような分け方であっても問題が生じることは基本的にはありません。
財産が金銭であれば、1円単位で分けることができます。
また、価値の低い財産しかないのであれば、複数いる相続人の中で1人を除いて辞退するという方法も考えられます。
しかしながら、不動産の場合は、価値が大きいことが多い上、相続人の誰かだけが取得すると、あまりに不公平な結果となることが多く、遺産分割協議がまとまらないという事態が生じることがあります。
次から、不動産の分割方法についてどのような選択肢があるのか、代表的なものについて挙げます。
2 不動産の遺産分割方法①(現物分割)
現物分割とは、不動産をそのまま、特定の相続人に名義変更することで分ける方法です。
例えばⅩという方が亡くなり、その子AとBの2人の相続人がいたとします。
相続財産が土地と家であった場合に、Aが土地、Bが家を受け取るという分け方です(分け方1)。
また、Aが土地と家を受け取り、Bは何も受けらないという分け方も可能です(分け方2)。
現物分割の特長は、合意さえ成立すればよく、特別な計算や処分を要しないため、手続等が簡易な点にあり、不動産の遺産分割方法の原則的方法といえます。
そのため、相続人間に特に争いが生じない場合は、この現物分割がなされることが多いです。
ただし、相続人間で争いがある場合は、選択することが難しく、相続する不動産が1つの場合は、相続人間で争いがないとしても不公平感から心情的に選びにくい選択でもあります。
3 不動産の遺産分割方法②(代償分割)
代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
現実に分けることができない不動産を受け取ったことによる不公平を受け取った人のポケットマネーから別の相続人に支払う(代償金を支払うこと)で解消するということです。
先の「分け方1」の例ですと、土地が2000万円の価値で家が1000万円であるとすると、Aが1000万円分Bより多く取得することになるため、AがBに対し、500万円支払うことを約束するという分け方です(分け方3)。
A
土地(2000万)-500万(Aの預貯金等から)=1500万
B
家(1000万+500万円=1500万円)。
代償方法の特長は、相続人間で平等を図りつつ、相続財産を残すことができることにあります。
思い出のある実家や賃料収入が見込める不動産など売りたくない不動産がある場合に選択される方法です。
ただし、不動産を受け取る相続人に代償金を支払うだけの資力がなければ選択することができません。
また、代償金の額を決めるためには、基本的に不動産の価格を決める必要がありますが、実際に売るわけではないので、その不動産の価格は相続人間で決める必要がありますが、そこで相続人間の争いが生じるケースもあります。
不動産の価格の決め方に厳密なルールはありませんが、固定資産税評価額、相続税評価額、不動産会社の査定価格などの数字を参考にしながら決めることが多いです。
4 不動産の遺産分割方法③(換価分割)
換価分割とは、遺産を売却等で換金(換価処分)した後に、その代金を分配する方法です。
先の例でいえば、土地と家を売却して3000万円に変えて、AとBがその売却代金から1500万円ずつの現金を得るという分け方です(分け方4)。
換価分割の特長は、相続財産を処分して得られた金銭を分ける方法ですので、代償分割とは違い、分割前に代償の資力を有しないとしても、選択可能であるという点にあります。
ただし、計算上の都合で上記の例では省きましたが、素人が不動産を売却するためには、不動産会社の仲介等が必要となりその分手数料がかかります。
また、家については、中古だと買い手が見つからないということで、家については取り壊し、土地を更地として売却することがありますが、その場合は、取り壊し分の費用が掛かり、実際に手元に残る金額はその不動産の価値よりも小さくなることがあります。
そして、不動産を売却する以上、譲渡所得税などの税金が発生し、申告が必要となる場合もありますので、注意が必要な点が多いです。
5 不動産の遺産分割方法④(共有分割)
共有分割は、遺産の一部又は全部を具体的相続分に従い共有取得する方法である。
先の例でいえば、遺産である土地と家を売らず、AとBの1/2ずつの共有名義とするという分け方です(分け方5)。
共有分割の特長としては、代償金を支払うこともできず、処分が困難あるいは相続人が残したいと考えている場合に選択される方法です。
ただし、共有とした不動産を処分などする場合は相続人全員の同意が必要とするなどの負担が生じます。
また、AとBが納得して共有していたとしても、Aが亡くなりその子CとDが相続することとなることがありますが、その場合は、その不動産を処分するのにB、C、Dの同意が必要となり、より不動産の処分が難しくなるというように、将来の手続がより複雑になる可能性も生じます。
共有分割は選択肢というより、上の3つができない、あるいは3つの方法のいずれかでは、公平性を害する場合の帰結といえます。