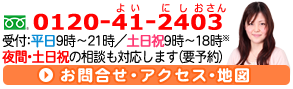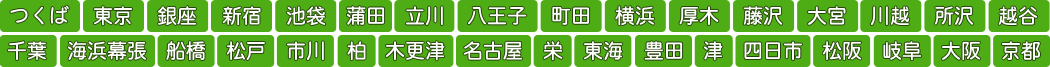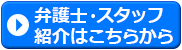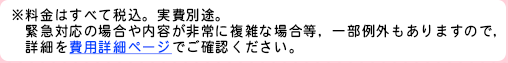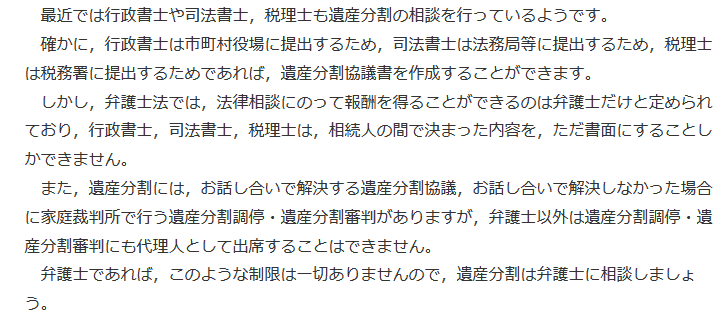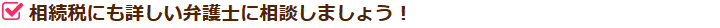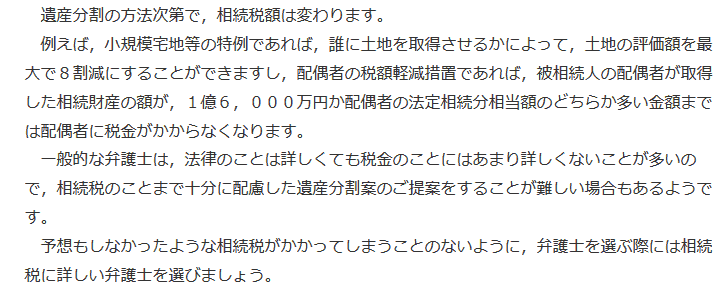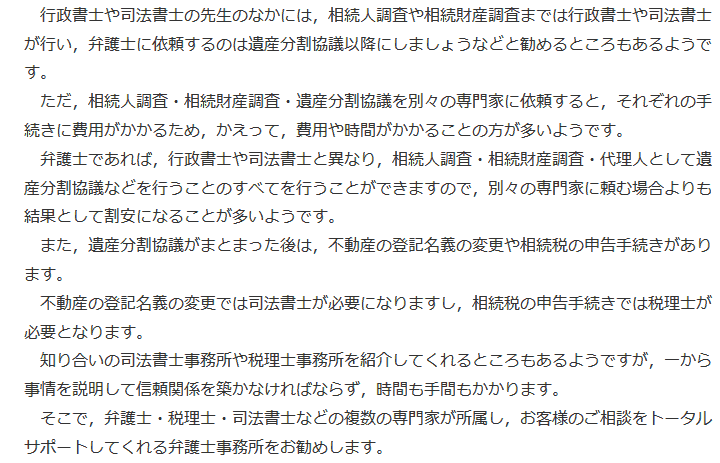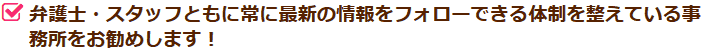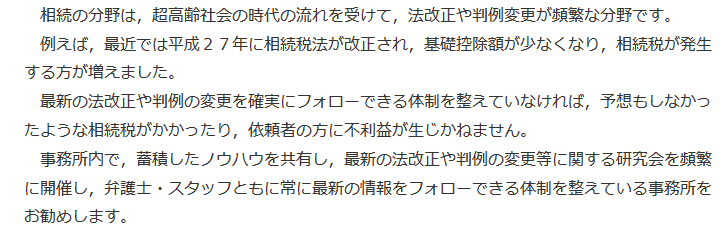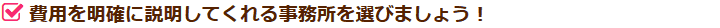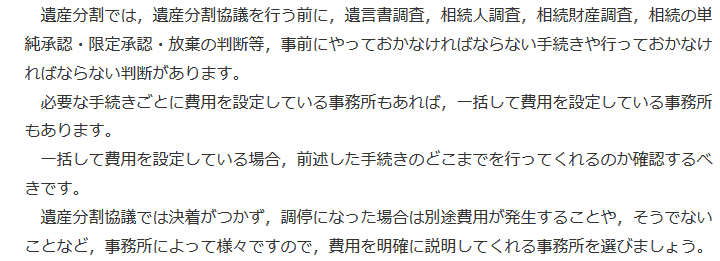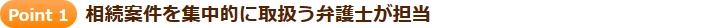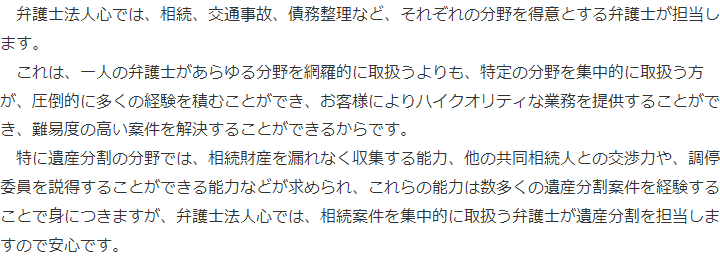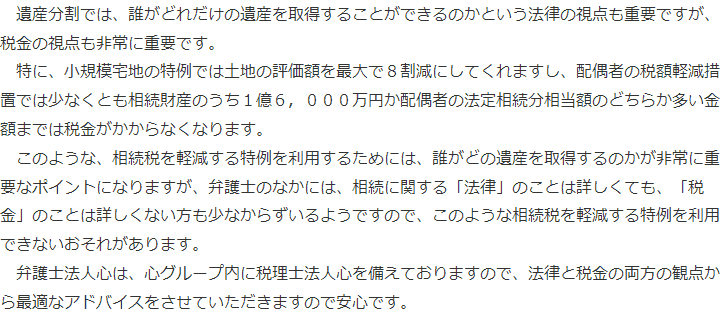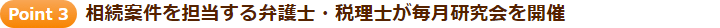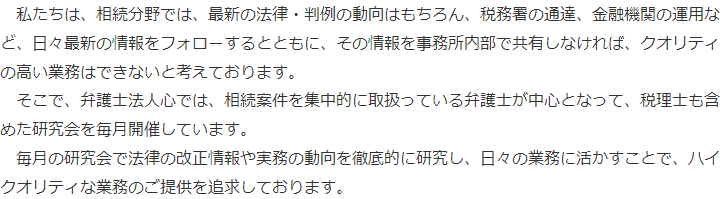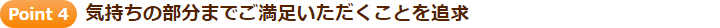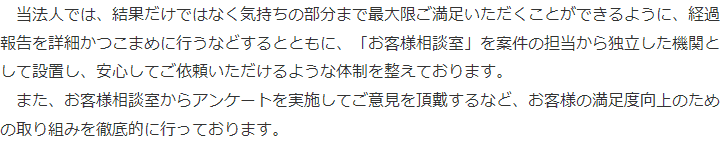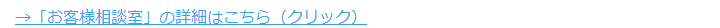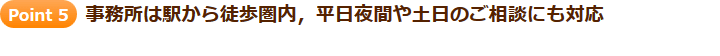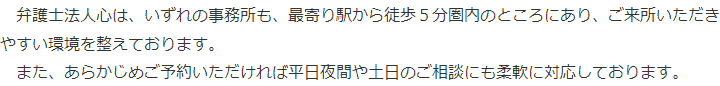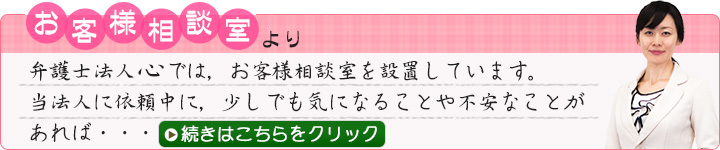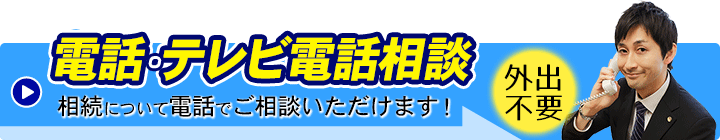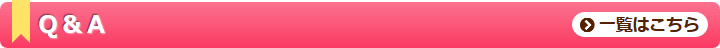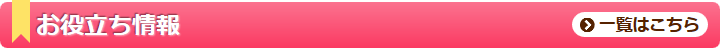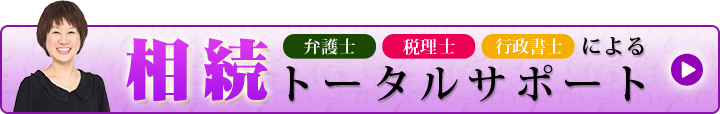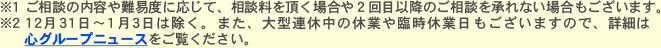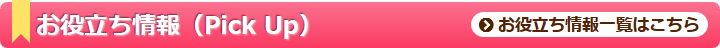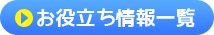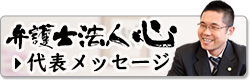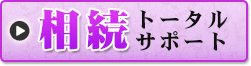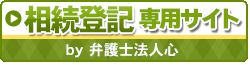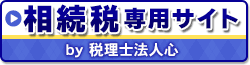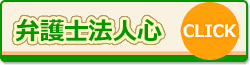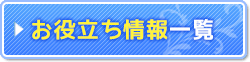- なぜ相続人調査が必要なのですか?
- 相相続人を確定しないで遺産分割協議をするとやり直しが必要になる場合もあります。また,後の相続手続きでは相続人が確定できる戸籍謄本等の提出が必要になります。遺産分割協議を始める・・・続きはこちら
- 遺産分割協議はどのようにすればいいですか?
- 原則として相続人全員で話し合いをします。亡くなった方の財産(遺産)をどのように分けるか決める話し合いを,遺産分割協議といいます。亡くなった方が遺言書を残されている場合には,・・・続きはこちら
- 遺産分割協議書は作らなければいけないですか?
- 義務ではないですが,作成をお勧めしています。遺産分割協議書とは,遺産分割協議が終了した際に,どのような内容を決めたのかを文書として記載したものです。遺産分割協議書は,必ず作成・・・続きはこちら
- 相続財産調査はどのようにすればいいですか?
- 被相続人の残している財産資料を手掛かりに,必要に応じて関係機関に問い合わせをします。相続財産の一部を把握せずに遺産分割協議をした場合,その後に新たに相続財産が発見されると,そ・・・続きはこちら
よくある質問はこちら
遺産分割を初めて行う際は疑問も多数生じるかと思います。名古屋でご相談をお考えの方の疑問を解消するため、こちらのページを役立てていただければ幸いです。
- 嫡出子と非嫡出子
- 婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子,そうではない子を非嫡出子といいます。日本の民法では,長い間,相続において,その相続分が非嫡出子は嫡出子の2分の1であるとされてきました(旧民法900条4号但書)。しかし,平成25年9月4日に,最・・・続きはこちら
- 代襲相続
- 1 代襲相続とは 被相続人に子どもが二人おり,そのうちの一人は亡くなっていて,その子どもが二人いた場合,子どもが相続人であると形式的に考えると,被相続人の子どもが全て遺産を手に入れることになり,孫に当たる二人には,全く財産が入らないこと・・・続きはこちら
- 特別受益
- 1 特別受益とは 被相続人から,婚姻費用や家を買ってもらったなど,被相続人の生前に贈与を受けた者や,遺言により贈与を受けた者がいる場合に,これを全く無視してしまうことは,非常に不公平です。ですから,この場合には,贈与を受けた財産の価値を・・・続きはこちら
遺産分割に関する情報
遺産分割がどういうものかはなんとなくイメージができても、詳しくはご存じない方も多いかと思います。こちらに様々なお役立ち情報を掲載していますので、ご覧ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2024年4月25日
その他
相続手続きの期限
ご家族が亡くなると、市区町村役場、年金事務所、各種金融機関などで、相続の手続きを行うことになります。これらの手続きの中には、期限が決められているものもあるため、注意が必・・・
続きはこちら
2024年2月5日
方法
遺産分割の証明書
遺産分割が成立しても、亡くなった人名義の不動産の名義変更、預貯金の払戻を行うことができなければ、本当の意味で問題が解決したことにはなりません。これらの手続を進めるために・・・
続きはこちら
2023年12月7日
方法
相続人が認知症の場合の遺産分割方法
相続人のうちの誰かが認知症の場合、認知症の程度によっては、遺産分割ができなくなる可能性があります。例えば、認知症で判断能力がない人がいる場・・・
続きはこちら
2023年10月4日
制度
生命保険は遺産分割の対象になるのか
生命保険は、契約内容により受取人の名義になっている人に払い戻されます。そのため、保険金を受け取るにあたっては、遺産分割を行う必要はありません。名義人が被相続人・・・
続きはこちら
2023年9月12日
制度
遺産分割調停・審判の管轄
亡くなった方が遺言書を残していなかったり、相続人の間で遺産分割の話し合いができなかったりした場合には、遺産分割調停や審判といった裁判手続きをする必要があります。この場合・・・
続きはこちら
事務所の所在地
名古屋駅から徒歩2分など、アクセスしやすい場所に事務所があり、ご相談にお越しいただきやすくなっています。詳しい場所についてはこちらをご覧ください。
遺産分割の手続きの流れ
1 遺産分割の流れ
一般的な遺産分割手続きの流れは、①相続人の調査、②相続財産の調査、③相続人同士の話し合い④遺産分割協議書の作成といった形になります。
それぞれどのように行うのか、各種相続手続を進めるうえでの注意点を知っておくことが大切ですので、こちらで解説していきたいと思います。
2 相続人の調査

⑴ 相続人調査の必要性
まず、遺産分割を始めるにあたっては、相続人の範囲を確定することが必要です。
相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行ってしまうと、遺産分割協議自体が無効になってしまいます。
過去には、遺産分割協議がまとまった後に、相続人に養子がいたことが発覚し、遺産分割協議をやり直さなければならなくなった事例もあります。
また、相続人を調査したところ、異母兄弟や異父兄弟がいたことが発覚したケースもあります。
そのため、遺産分割協議を進めるうえで、まずは相続人の範囲を確定することが必要です。
⑵ 具体的な調査方法
具体的な相続人の調査方法としては、戸籍をたどることが最も確実です。
戸籍は、本籍地がある市区町村役場で取得することができます。
なお、戸籍をたどる場合は、改製原因や除籍等の戸籍の種類等、戸籍についての専門的な知識が必要になりますので、ご不明な点等ありましたら、専門家にご相談ください。
3 相続財産の調査
相続人が確定したら、相続財産を把握する必要があります。
具体的な相続財産の調査方法は、不動産の場合、固定資産税納税通知書や登記情報、名寄帳等で調べるといったものになります。
例えば、市役所で固定資産評価証明書を発行してもらい、所在と評価額を調査することができる場合もあります。
また、預貯金関係を調べる場合は、残高証明書や現存照会を取って、現在の預貯金残高を調査することもできます。
他方、借金関係については、CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)やJICC(日本信用情報機構)などの機関に照会することで、カードや銀行ローン等を確認することができます。
このように、相続財産の調査には、手間と時間、知識が必要になりますので、ご不明な点等ございましたら、一度、専門家にご相談ください。
4 相続人同士の話し合い
相続人と相続財産が確定した後は、遺言書がある場合を除き、遺産の分け方について、相続人同士で話し合いをする必要があります。
5 遺産分割協議書の作成
遺産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の具体的な作成方法は、誰が遺産をどれだけもらうかを記載し、最後に相続人全員で署名押印をします。
遺産分割協議書の内容が間違っていたり、財産に漏れがあった場合などには、預貯金を解約できなかったり、再度遺産分割をしなければならなくなることもありますので注意が必要です。
なお、遺産が預貯金のみの場合は、遺産分割協議書を作成する必要がないケースもあります。
法定相続分
1 相続人が誰であるかにより異なります
相続人が誰であるかによって、それぞれの法定相続分(相続する割合)が変化します。
ここでは、3つのパターンについて、それぞれの法定相続分がどうなるかを説明いたします。
2 子が相続人である場合
配偶者と子が相続人である場合には、配偶者が2分の1をとり、残りの2分の1を子が平等に分けます。
相続人が子のみである場合には、子が平等に分けます。
3 直系尊属が相続人である場合

配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)が相続人である場合には、配偶者が3分の2をとり、残りの3分の1を直系尊属が平等に分けます。
相続人が直系尊属のみである場合、父母の双方が生きていれば、両者が平等に分けます。
父母の片方のみが生きている場合には、祖父母が生きていても、父母の片方のみが遺産を全て取得します。
父母の双方が亡くなっている場合には、祖父母が遺産を平等に分けます。
4 兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者が4分の3をとり、残りの4分の1を兄弟姉妹が分けます。
このとき、両親の双方を同じくする兄弟の取り分が、両親の片方を同じくする兄弟の取り分の2倍となるようにします。
相続人が兄弟姉妹のみである場合には、兄弟姉妹が分けます。
この場合にも、両親の双方を同じくする兄弟の取り分が、両親の片方を同じくする兄弟の取り分の2倍となるようにします。
遺産分割は誰に相談すればよいか
1 遺産分割を本人たちだけで行うのは大変

⑴ 遺産が少額でも揉めることがある
遺産分割とは、被相続人の遺産を相続人間でどのように分割するかを決め、その決めた方法に基づいて遺産を相続する手続きを言います。
これを読まれている方の中には、「遺産は自宅と預貯金のみで少ししかないから、遺産分割をわざわざ専門家に頼む必要はない」と思った方もいらっしゃるかと思います。
ところが、全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割についての紛争は、統計を見ると遺産総額5000万円以下、1000万円以下を合わせた件数がほとんどを占めており、必ずしも遺産総額が多いから紛争になりやすいという訳ではないことが分かります。
また、よく遺産分割で揉める事例として、「自分は父の介護をして大変な思いをしたのに、何もしなかった兄弟と同額なのは納得できない」「長男だけは母から色々と物を貰っていたが、自分たちは何も貰っておらず、扱いが不平等だったのに、相続のときだけは平等とするのは貰い過ぎだ」といった、相続人間の不平等感に由来するものが多く見受けられます。
このような相続人間の感情のもつれによる紛争は、遺産が多いかどうかとは別問題ですので、このことからも、遺産額が少ないからと言って揉めないという訳ではないことが分かるかと思います。
⑵ 遺産の分け方以外にも必要な手続きが多い
遺産分割を行うためには、その前提として、相続人が誰であるかを確定させるための相続人調査や、遺産範囲を確定させるための財産調査といった手続きを行う必要があります。
相続人調査では、被相続人の戸籍を出生から死亡まで取り寄せて、相続人に該当する人を探す必要があり、財産調査では、被相続人が所有する不動産や銀行口座などについて、自宅を探したり、役所や銀行に問い合わせて確認したりする必要があります。
手続きの中には郵送で行えるものもありますが、本人が窓口で対応しなければならない手続きもあります。
市役所や銀行が開いている時間は通常平日の日中に限られますので、仕事をされている方にとっては仕事の合間を縫って手続きを行わなければならないなど、かなりの負担となります。
加えて、調査の方法や、戸籍の見方など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。
また、遺産総額が基礎控除額を超えていて、相続税の申告が必要となるケースでは、原則として相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割を終えている必要があるため、これらの手続きを10か月以内に終える必要があります。
もし10か月以内に終えられなかった場合は、一旦仮の申告をして、後から修正申告等を行うといった、面倒な手続きを経なくてはならなくなります。
2 相続で困ったら相続・税務の両方に取り組んでいる事務所に相談
⑴ 弁護士に頼むメリット
上記のように、相続の場面では、財産調査や相続人調査など、行わなければならない手続きがたくさんあり、しかも、それらは一定の期間内に済ませなければ多大な不利益を被る場合があるなど、ご自分で行うには負担の大きいものです。
また、遺産分割について当事者で話し合うのみでは、その分割方法が法的に妥当なのかどうかの判断ができず、本当は主張できるはずの権利を失ってしまうおそれもあります。
弁護士に一切の手続きを任せれば、遺産分割に必要な手続きを代わりにしてもらうことができますし、法律に則った方法での分割を主張することもできます。
さらに、相続案件を多数取り扱っている弁護士であれば、その経験からどのような点が揉めやすいか、最終的にどのような結論になるのかなどの見通しを立てることができますので、遺産分割協議をスムーズに進めることができる可能性が高くなります。
⑵ 相続と税務の両方に取り組んでいる事務所の強み
相続は税務の問題と非常に密接した関係にあります。
なぜなら、分割方法によっては、相続税の控除が使えなくなったり、思わぬ税負担が生じてしまったりする場合があるからです。
したがって、遺産分割では、税務の観点からどうなのかというチェックも必要です。
もっとも、別々の弁護士と税理士に依頼すると、手間も費用もかかってしまうおそれがあります。
相続と税務の両方に取り組んでいる事務所であれば、弁護士と税理士が連携することにより、この手間と費用を節約でき、かつよりよい解決に導くための提案を行えることが期待できます。
遺産分割にはどのような方法があるか
1 遺産分割の各方法

⑴ どのような分割方法があるか
遺産分割の主な方法としては、現物分割、換価分割、そして代償分割の3種類があります。
各分割方法の違いについて、例として相続財産が土地のみ(路線価3000万円)で、相続人が子3人というケースを考えてみたいと思います。
⑵ 現物分割
相続財産そのものを相続人で分割して取得することを、現物分割といいます。
上記の例の場合、相続人で不動産を3分割してそれぞれ取得すれば、現物分割の方法により相続財産を分割したことになります。
現物分割には、相続財産をそのまま分けるだけなので分かりやすく、手続きも簡単であるというメリットがある一方で、公平に分割するのが難しいというデメリットがあります。
上記例では、相続財産が土地のみですので、公平に分ける場合は分割した土地の価値が3分の1ずつになるよう測量して分筆すればよいのですが、相続財産が建物の場合だと、建物を物理的に3等分するわけにはいかないため、現物分割には向きません。
また、相続財産が土地だけであっても、分割により道路に直接出られない袋地が生じてしまう場合などは、誰もその袋地の取得を希望せず、分割案がまとまらないということも考えられます。
⑶ 換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して一旦金銭にし、その金銭を相続人で分割する方法です。
上記の例だと、相続財産を売却して得られた3000万円を、相続人3人で1000万円ずつ分割することになります。
金銭を等分で分割することは容易ですので、分割自体での争いを減らせるというメリットがありますが、前提として相続財産を売却する必要があるため、あまり需要のない田舎の土地など、売却の見込みが低い相続財産には向いていない方法です。
また、先祖代々の土地を手放したくないなど、売却について相続人のうち一人でも反対している場合には、この方法は採れないということになります。
⑷ 代償分割
代償分割とは、ある遺産を取得する代わりに、他の相続人には金銭(代償金)を支払うという形で解決する方法をいいます。
この方法は、例えば、相続人の一人は相続財産である不動産に住んでいて取得を希望しているが、他の相続人は遠方に住んでおり現物の取得を希望しないといった場合によく用いられます。
上記例だと、相続人の一人が不動産を単独で取得し、残りの二人にそれぞれ1000万円ずつ代償金を支払うことになります。
相続財産を取得したい相続人と、現物はいらないが現金で取得したい相続人どちらのニーズも満たすことができる点がメリットとして挙げられますが、単独で取得する相続人に代償金を支払えるだけの資力がなければ、この方法は採れません。
また、実際に売却するわけではないため、相続財産の価値の評価方法について争いが生じる可能性があるといったデメリットもあります。
2 どの遺産分割方法が良いか
上記3種類のうち、どの方法が最も適しているかは、相続人だけで判断するのではなく、相続と税務の双方に熟知した弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、どの方法が良いかは、相続人らの希望だけでなく、相続税や所得税の問題など、その他の事情も考慮して総合的に検討しなければ判断できないからです。
特に不動産が相続財産となっている場合には、場所によってはある程度の地価になることもありますので、この問題は重要になってきます。
当法人は、駅の近くに事務所を設けているため、お仕事の帰りや用事のついでに気軽に相談することができます。
遺産分割に関する問題解決を得意とする弁護士がいますので、遺産分割の方法でお困りの場合には、ぜひ当法人へご相談ください。
遺産分割のお悩みは弁護士へ
1 遺産分割で揉めていなくても弁護士に相談を

「弁護士はトラブルになった時に依頼する」と思われている方も多くいらっしゃいます。
しかし、たとえ相続人間で揉めていなかったとしても、弁護士に相談したほうがよいといえます。
なぜなら、遺産分割においては、最終的に遺産分割協議書を作成し、預貯金や不動産の名義変更を行うことが多いですが、この協議書の書き方を誤ってしまうと、作成し直すことになり、後々、相続人間でトラブルになってしまう可能性があるためです。
実際、弁護士以外の専門家が作成した遺産分割協議書の内容が不十分であったため、後々、相続人間で裁判に発展するまでの争いになったケースもあります。
そのため、後々のトラブルを防止するためにも、遺産分割や協議書の作成については弁護士に相談することをおすすめします。
2 弁護士以外は遺産分割の代理人になれない
そもそも、弁護士以外の専門家は遺産分割の代理人になれず、他の専門家が代理人になっている場合は、違法となります。
専門家の中には、裁判所に提出する書類を相続人に代わって作成する人もいますが、弁護士でない以上、脱法行為の可能性があり、また、そういう人は遺産分割に関する知識も間違っている場合もあります。
また、弁護士以外の専門家が作成したネットの記事の中にも、誤った知識が記載されているものも多々ありますので、注意が必要です。
誤った情報に振り回されないよう、遺産分割のお悩みは、基本的に弁護士に相談した方が良いでしょう。
3 遺産分割に関する裁判手続き
遺産分割について、相続人間の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所において遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割調停では、裁判所を通した話し合いとなり、それでも解決しない場合は、遺産分割審判といい、裁判所が遺産の分け方を決めます。
また、遺産分割審判が出たとしても、遺産を相続人間で共有取得させる共有分割の審判が出ることもあり、その場合は、地方裁判所において共有物分割訴訟を提起する必要がある場合があります。
このように、遺産分割においては、調停、審判、訴訟といった裁判所での手続きが必要になる場合があります。
裁判に関する実務的な知識・経験を有しているのは弁護士のみであり、代理人になれるのも弁護士のみですので、弁護士にご相談ください。
遺産分割に詳しい弁護士に依頼するメリット
1 遺産分割に詳しいか否かで結果が全く異なる可能性がある

遺産分割は、弁護士に依頼したところで結果が変わらないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、少しでも多く財産を取得したい、早く遺産分割を終えたいと考えている人ほど、弁護士に依頼するメリットが多くあります。
さらに、依頼する弁護士が遺産分割に詳しいかそうでないかで、大きく結果が異なる場合があります。
そこで、遺産分割に詳しい弁護士に依頼するメリットを、以下の3点からまとめていきます。
① 期間が短くなる可能性がある
② 具体的な権利・主張を余すことなく主張できる
③ 遺産の評価を適切に行ってくれる
2 期間が短くなる可能性がある
遺産分割にかかる時間は、1か月から4~5年かかるものまであります。
例えば、相続人の間で、誰がその財産を取得するのかについて、折り合いがつかない時は、遺産分割調停や遺産分割審判を行っていくことになります。
この遺産分割調停や審判は、結果が出るまで数年単位で時間がかかることも多く、長い時間と金銭、労力を使用することになります。
しかし、遺産分割に詳しい弁護士に依頼した場合、相手方と早期に連絡を取り、これらのリスクを説明した上で、具体的な分割案を即座にまとめることが期待できます。
実際に、弁護士に依頼いただいたもので、もめていた相続人同士で早期に遺産分割を実現できたケースも多く存在しています。
3 具体的な権利・主張を余すことなく主張できる
遺産分割では、以下のような権利・主張をして、解決を目指すことになります。
① 遺留分
② 特別寄与料
③ 寄与分
④ 特別受益
⑤ 遺産の評価
⑥ 遺言の無効
⑦ 分割方法
⑧ 遺産確認
⑨ 使途不明金
⑩ 価格弁償請求
これらの権利を行使するには、厳格な要件の該当性を判断し、どのような効果が発生するかを判断する必要があります。
相談者の方の話を聞いたうえで、裁判所が採用しやすい主張と証拠を厳選するためには、遺産分割を集中的に扱っている弁護士に依頼することが大切です。
4 遺産の評価を適切に行ってくれる
例えば、遺産に不動産があった場合に、その不動産の価格をどう評価するかが問題となることがあります。
不動産の価格を決定する際に参照する証拠の中でも、依頼者に有利な証拠や、依頼者に不利な証拠があります。
実際に、固定資産税評価額証明書や不動産事業者の見積書等、状況に応じて提出するべき証拠が変わってくるのも多いです。
そして、遺産分割に詳しい弁護士であれば、これらの証拠の有利不利を判断し、依頼者の方にとって有利な遺産評価を行うことが期待できます。
遺産分割協議書作成時の注意点
1 遺産分割協議書を作成する際の主な注意点

遺産分割協議書を作成する際の注意点について、まとめると以下のとおりになります。
① 相続人全員の実印による押印
② 財産の記載を明確に行う
③ 複数ページになる際は、全ページに契印を行う
④ 法定代理人が遺産分割協議に参加する時は、特別代理人の選任
以下、解説していきます。
2 相続人全員の実印による押印
遺産分割協議書には、相続人全員の実印による押印を行います。
遺産分割協議書は、遺産の今後の所有権の帰属先を決定する重要なものですので、相続人の全員が真摯に合意したことを証するために実印での押印が要求されるのです。
また、実際に第三者(法務局や銀行等)に対して遺産分割協議書を提出する際は、印鑑証明書を添付することが必要となります。
遺産分割協議書に押印してもらう際には、同時に印鑑証明書をもらうようにしましょう。
3 財産の記載を明確に行う
上述のとおり、遺産分割協議書を作成した後、その書類は第三者に提出する必要があります。
そのため、どのような遺産が分割されたのかを明確に認識できるように記載していく必要があります。
例えば、遺産に不動産がある場合には、以下の情報を記載します。
①土地
所在 〇〇市○〇町
地番 ○〇番
地目 宅地
地積 ○〇㎡
② 建物
所在 〇〇市○〇町
家屋番号 ○〇番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○〇㎡
2階 ○〇㎡
また、銀行口座がある場合には、以下の情報を記載します。
○〇銀行 ○〇支店 普通預金 口座番号1234567
このように、財産の明示を行わなければ、相続手続きが進められない場合がありますので、記載の仕方には注意が必要です。
4 複数ページになる際は、全ページに契印を行う
遺産の量が多い場合や、個別に受け取るべき財産が多い場合には、遺産分割協議書が複数のページになることがあります。
このような場合には、すべての頁に契印を行うようにしましょう。
5 法定代理人が遺産分割協議に参加する時
法定代理人が遺産分割協議に相続人として参加する場合、法定代理人と未成年者は、法定代理人の取り分が多くなると未成年者の取り分が減るという点において「利益相反」の関係にあることになります。
例えば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となる場合には、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てを行い、遺産分割協議を行う必要があります。